赤ちゃんに話しかけるのって意味あるの?
赤ちゃんに語りかけてはいるものの、
- 本当に意味あるのかな?
- 内容なんてわかってないのでは?
と思ったことはありませんか?
僕自身、そう疑問を抱きながらも、日々の育児の中で声をかけることを続けてきました。
結論から言うと、「語りかけ育児」には確かな効果があります。
科学的な研究でも裏づけられており、親子の絆づくりだけでなく、赤ちゃんの脳・言語・情緒の発達にも影響することがわかってきています。
この記事では、「語りかけ育児」の意味や効果など、科学的な根拠や僕自身の実践例を交えて詳しくご紹介します。
声は聞こえている?赤ちゃんの聴覚の発達

赤ちゃんは実は、妊娠20週ごろから音を聞き取れるようになり、妊娠30週以降には、外の音をかなりはっきりと認識していると言われています。
特に、母親の心音や血流音、そして声は、胎内でも日常的に聞いている音のひとつです。
そのため、赤ちゃんは生まれた瞬間から聴覚がある程度発達しており、すでにママ・パパの声に親しんでいる状態です。
実際に、カナダの研究では、生後24時間以内の新生児が母親の声と他人の声を聞き分けていることが確認されており、脳の反応も異なることが示されています。
「ちゃんと聞こえてるのかな?」と不安に思う必要はありません。
赤ちゃんはすでに、あなたの声をよく知っていて、しっかりと聞いています。
その声は、赤ちゃんの安心感を育み、脳や心の発達を支えているのです。

生まれた後はもちろんだけど、生まれる前から「お腹に話しかける」ことにもちゃんと意味があるんたこね~
語りかけの科学的効果:脳と言語が発達する
語りかけが多いほど、赤ちゃんの言語能力が高くなると言われています。
更に、米国で3年間にわたって親子の会話を調査した有名な研究では、語りかけの量と語彙の豊かさが、子どもの言語能力だけでなくIQにまで影響するという結果が出ています。
特に、1時間あたり英単語2,100語程度の語りかけが理想的だとされています。
これは日本語に置き換えると、大人が普通に会話しているペースとほぼ同じです。
たとえば、「今おむつ替えてるよ〜」「今日はいい天気だね」「お腹すいたかな?」など、何気ない声かけを絶えず続けるくらいのイメージです。
ですので、「語りかけ」というのは単なる「育児のコツ」ではなく、子どもの将来を左右する重要な刺激なのです。
また、高くゆったりとした話し方(マザリーズ)は、乳児の脳にとって聴き取りやすく、発語や言語習得の基礎をつくるのに役立つと証明されています。

赤ちゃんに限らず、子供に話しかけるときは自然と高い声でゆったりと話しかけたくなるけど、ちゃんと理にかなっているんたこね~
語りかけがもたらす情緒の安定と信頼関係
赤ちゃんは言葉の意味はわからなくても、親の表情・声色・抑揚から感情を読み取っています。
厚労省の指針でも、優しい語りかけが赤ちゃんの情緒を安定させ、親子の信頼関係(愛着)の土台になると明記されています。
逆に話しかけがない・無表情だと、赤ちゃんは不安を感じ、表情や反応も乏しくなってしまうことがあるそうです。

どうせ意味が分からないから…と話しかけないのは勿体ないたこね~
実際にやっていることは意味ある?僕の実践内容

僕が毎日行っている語りかけの例と、それがどんな効果を持つ可能性があるのかを、根拠とともに整理してみました。
| 僕の実践内容 | 期待される効果 |
|---|---|
| 高い声・大げさな表情で話す | 赤ちゃんの脳が認識しやすいため注意を引きやすく、理解が促進される。 |
| 「あー」「うー」という喃語に「うんうんそうだね」と相槌を打つ | 双方向のやりとり(擬似会話)は言語習得に重要。喃語に応答することで発語意欲が育つ。 |
| 名前を呼ぶ | 声主や自分の名前の音を識別する力が育つ。特に母親の声には反応が強く、高い効果が期待される。 |
| 歌に名前を入れて歌う | 音楽+言葉の繰り返しは記憶定着に効果的。表情と声を一緒に届けることで情緒の発達も促される。 |
| 毎日の決まった場面で同じ言葉をかける(例:「おはよう」「ねんねの時間だよ」) | ルーティン言語により予測・理解・安心感が育つ。生活リズムや文脈理解にもつながる。 |
| 抱っこしたときに「あったかいね~」などと声をかける | スキンシップとポジティブな言葉の組み合わせが、感情と言語の連動と愛着形成を促す。 |
| ミルクや授乳のときに「飲んでるね〜」などと声をかける | 語彙+感覚体験の一致により、言葉と行動の対応関係を学習しやすい。 |
| 状況を言葉にする(実況) | 今している行動を実況中継することで、語彙力と文脈理解が育つ。 |
| 家の中を散歩しながら、「これは時計だよ」「あっちはテレビだね」など語りかける | モノの名前の理解(語彙の発達)に直結。空間認識と言語の統合にも効果あり。 |
| 「つんつん」「ぽんぽん」など擬音を言いながらほっぺたなどに触れる | 語感・音の認識と触覚の結びつきができる。感情の発達や愛着形成にも貢献。 |

「なんとなくやってたこと」に、ちゃんと意味があるって分かると嬉しいたこ〜
無理せず取り入れるコツ:頑張らなくてもOK

語りかけが良いことは分かっていても、毎日赤ちゃんと向き合っていると、
- 「何を話していいか分からない」
- 「そんなにたくさん話せない」
と感じてしまう日もあるかもしれません。
でも、完璧にやろうとする必要はまったくありません。
たとえば、以下のようなちょっとした意識だけでも立派な語りかけになります。
- おむつ替えのときに「すっきりしたね〜」
- 抱っこしながら「いい匂いだね~」
- ミルクを飲ませながら「いい飲みっぷりだね~」
これらはすべて「実況中継」や「感情表現」の語りかけです。
話す内容が分からなくても、今感じたことやしていることを言葉にするだけで十分です。
また、声をかけるのが難しいときは、笑顔やアイコンタクトでもOK。
赤ちゃんは親の表情や声のトーンからも、たくさんの情報を受け取っています。

気負わず、できるときに・できるぶんだけで大丈夫たこ〜
6か月以降も効果は続く:将来の知能や社会性にも関係
語りかけの効果は新生児期に限ったものではありません。
むしろ6か月以降〜幼児期にかけて、その影響はさらに大きくなっていきます。
たとえば、米国の長期研究では、3歳時点の語彙量が、その後のIQや学業成績に強く相関していたという結果が出ています。
また、カナダの研究では、2歳までに家庭での会話が多い子どもは、4歳時点で社会性(共感力や自己制御能力)が高くなる傾向も確認されています。
このように、「赤ちゃんにたくさん話しかけること」は、言語だけでなく、知能や人間関係の力(非認知能力)にも影響するとされているのです。
もちろん、すべてが語りかけだけで決まるわけではありませんが、
親とのやりとりは、赤ちゃんにとって最高の知育であり心の栄養だと言えます。

語りかけって、将来の「生きる力」にまでつながっていくんたこね〜
おわりに

「赤ちゃんに話しかけても意味ないのでは?」
そう感じる瞬間は誰にでもあります。
でも、実際には赤ちゃんの耳も心も、ちゃんとパパ・ママの声を受け取っていて、脳もぐんぐん育っているということが、数々の研究で明らかになっています。
僕自身、専門家でもなく、育児の経験もまだ浅い中で手探りの毎日ですが、
「声をかけることには確かな意味がある」
そう思えるようになってから、日々の関わりがより前向きで楽しいものになりました。
赤ちゃんに話しかけるのに、難しい言葉や知識は必要ありません。
その日感じたこと、していることを素直に言葉にするだけで、立派な語りかけです。
ぜひ、無理せず・楽しく、あなたらしい語りかけ育児を続けていきましょう!

僕はおしゃべりだから、何でもかんでも子供に話してるたこ~
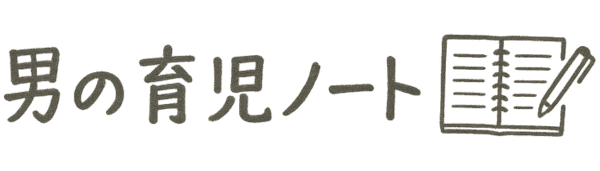

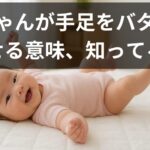

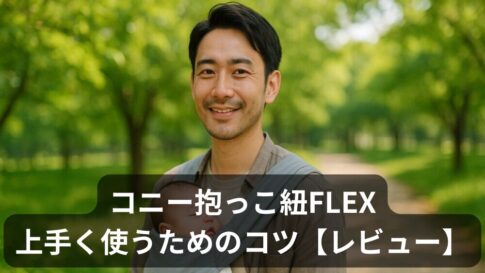

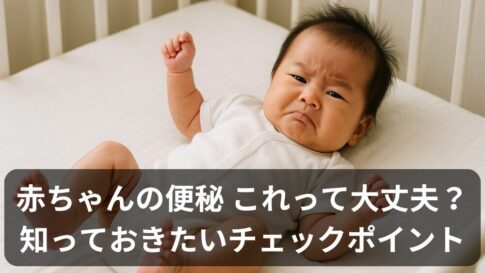


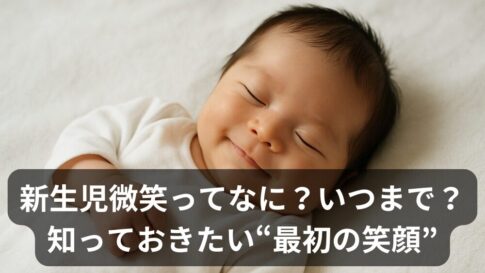
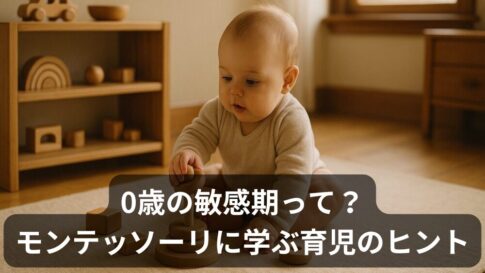







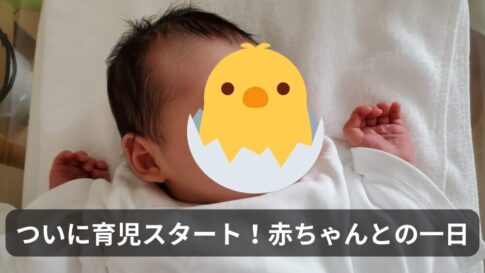

赤ちゃんは何気ない声かけからたくさんのことを学んでいるんたこよ〜