はじめに:子どもが生まれる前に、出来ることはしておきたい
何をしたらいいか分からないけど、何かはしておきたい
妻の妊娠中、出産が近づくにつれて、僕はそんな風に思うことが増えました。
育児グッズを揃える、環境づくり、夫婦でのすり合わせ、心の準備など、プレパパにもやれることは実はたくさんあります。
この記事では、僕自身が実際に「やっておいてよかった」と思っている準備を7つにまとめてご紹介します。
これからパパになる方の参考になれば幸いです。
①育休の制度を調べ、育休取得について職場と話し合った
- 育休とは何か
- 自分は対象なのか
- いつ取得できるのか
- 収入はどうなるのか
など、インターネットでとにかく調べました。
Youtubeには分かりやすい動画などもありますが、最新かつ正確な情報把握には、厚生労働省の育児休業制度特設サイトがおすすめです。
その後、会社の上司に育休を取得させてもらえないか相談しました。
かなり早め(出産予定日の約半年前)から動き始めたので、不安な気持ちを少しだけ軽くすることができました。
育休取得について上司と相談した結果はこちらの記事で紹介しています!
②育児の役割分担を夫婦で話し合った

「自然に決まるだろう」では、「何でやってくれないんだろう」「自分はこんなにやっているのに」というトラブルが生じる可能性があります。
我が家では産後の家事・育児の分担について事前に何度も話し合ったことで、我が家ではトラブルになることはなく、スムーズに産後の生活を送ることができました。
役割分担についてはこちらの記事で詳しく紹介しています!
③出産に向けて必要なグッズを早めに揃えておいた
入院、出産、退院後の子育てなど、分からないことばかりですよね。
僕も不安でいっぱいでした。
グッズを揃えることでその不安が和らぎ、「いつ生まれても大丈夫かも」とだんだん思えるようになりました。
実際に用意して良かったグッズについてはこちらの記事で詳しく紹介しています!
④育児できる環境を整えた

僕の住む北海道では、エアコンのない家もあります。
我が家も例に漏れずエアコンはありませんでした。
そこで、夏生まれの赤ちゃんに備えてエアコンを導入しました。
工事費込みで40万円以上かかりましたが、快適さは抜群です。
また、ベビーベッドの近くで寝るためにソファーベッドも購入しました。
子供の乗り降りのしやすさの観点から、軽自動車からコンパクトカーへの買い替えも検討中です。
追記:
子供の生後2か月現在、軽自動車ですが何とかなっています。
もう少し大きくなっていよいよ窮屈になったら買い替えます。

子供のいるいないに関係なく、とっても快適だからエアコンは付けるべきたこね~
⑤名前の案を出し合った
妊活開始時から、「男の子だったら」「女の子だったら」と名前の候補をお互いに出し合ってきました。
名前が決まってからは、毎日妻のお腹に話しかけていました!

名前が決まるだけでとっても愛おしい気持ちになったこ~
⑥実家に「いざというとき協力してほしい」旨を相談した
いざという時に頼れる存在は心の支え。
妻の両親は遠方に住んでいるため、近所に住む僕の両親に協力を依頼しました。
事前に話しておくだけでも安心感が違います。

すぐ保育園に入れる予定はないので、自分たちの時間が欲しくなったときは預けさせてね~とお願いしたこ~
⑦妊婦健診に付き添った

一緒に行くだけで、得られる安心感は想像以上でした。
エコーを一緒に見たり、先生の説明を共有したりすることで、「父親になる」という実感が湧いてきました。
妊婦健診で何をしているか知らないと置いてけぼりな気持ちになりますし、
妻も「来てくれて嬉しかった、安心した」と言ってくれて、信頼関係が深まったと感じます。
妊婦健診についてはこちらの記事で紹介しています!
おわりに
妊娠中に男性ができることは限られていますが、それでもやれることはあります。
思いつく限りのことを行動に移したことで、少しですが産後に向けての準備ができたかも…という自信を持てていました。
これからパパになる方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。
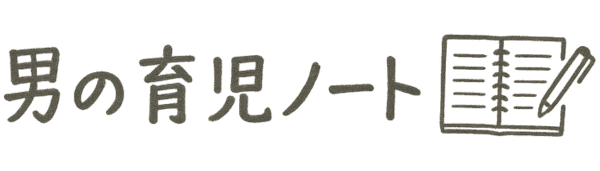

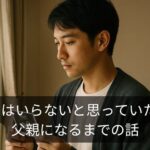

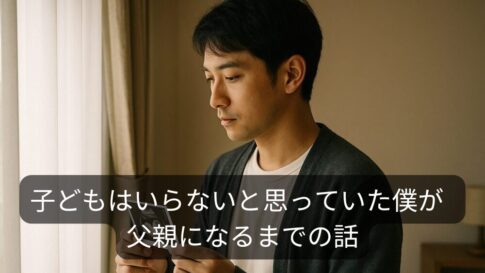



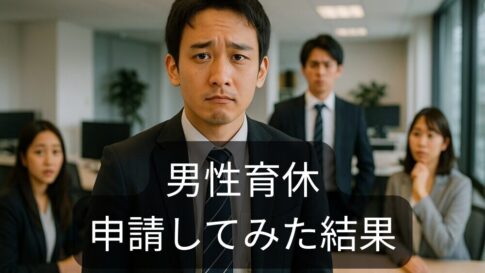
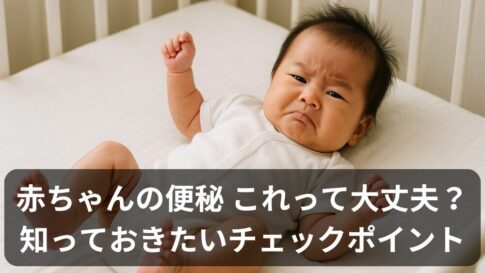



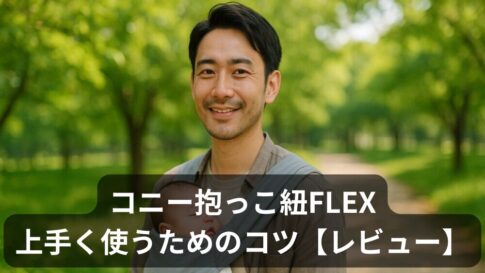

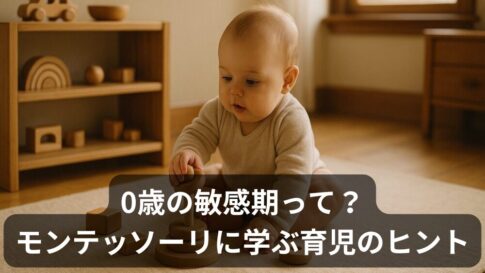


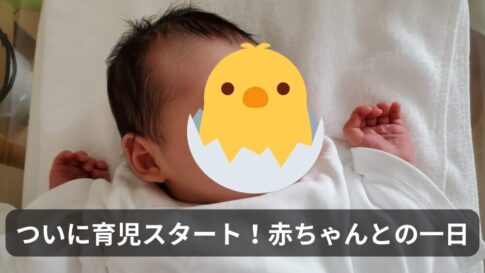

子供が生まれたのをきっかけに、夫婦仲が悪くなるなんて嫌たこね~