はじめに
最近よく聞く「モンテッソーリ教育」。
オバマ元大統領や将棋の藤井聡太さんも受けていたことで注目されましたが、「なんとなく良さそう」と思っている方も多いのではないでしょうか?
僕自身、子どもが生まれたのをきっかけにformieというサービスの「モンテッソーリトレーナー育成講座」を受講し、資格を取得しました。

学んでみて感じたのは、モンテッソーリ教育は0歳からでも家庭で実践できることがたくさんあるということと、我が家の教育方針にマッチしていたことでした。
我が家の教育方針
- 自分で選べるようになってほしい
- 色んなことに挑戦し、色んな経験をしてほしい
- 苦手・嫌いを無理に補おうとするよりは、得意・好きを伸ばしてほしい
- 自己肯定感が高く、幸福を感じながら過ごしてほしい
この記事では、講座で得た知識と、わが家での実践をもとに、0歳の赤ちゃんにできるモンテッソーリ的関わり方5つを紹介します。
モンテッソーリ教育とは?

モンテッソーリ教育は、イタリア初の女性医学博士「マリア・モンテッソーリ」が、100年以上前に提唱した教育法です。
僕の言葉でまとめると、「自分で選び、興味のあることに集中して取り組めるようサポートすることで、自主性・責任感・思いやり・集中力・非認知能力を育てる」教育法です。
「非認知能力」とは
意欲・協調性・忍耐力・創造性・感情のコントロールといった「目に見えにくい力」のことを指します。
(テストの点数などで数値化できる知識やIQのようなものは認知能力と呼ばれます。)
近年の研究では、学力や将来の社会的成功を左右するのは認知能力以上に非認知能力が重要だとされ、モンテッソーリ教育でも乳児期からこの力を育むことが重視されています。
モンテッソーリ教育の最大の特徴は、「子どもには生まれつき自分を育てる力=自己教育力が備わっている」という考えを前提に、
それを最大限引き出すため、子どもの発達段階に合った環境を整え、本人の自主性を尊重することにあります。
ですので教師や親は「教える人」ではなく「環境を整え、見守り、適切なタイミングでサポートする存在」として位置づけられています。
近年では脳科学や心理学の分野でもこの理論の有効性が支持されており、モンテッソーリ教育は今や世界110か国以上で実践されています。
日本でも藤井聡太さんやGoogle創業者らのエピソードを通して注目を集め、取り入れる家庭が増えています。
なぜ「0歳から」なのか?モンテッソーリ教育が重視する理由

0〜6歳は「人格の土台」が形成されるかけがえのない時期
モンテッソーリ教育では、人の一生を通じて最も重要な発達の時期は幼年期(0〜6歳)だとされています。
この期間で、人生に必要な能力の80%が備わるとも言われており、特に0〜3歳の「前期幼年期」は無意識の吸収期とされ、外からの刺激をまるごと取り込む特別な時期です。
これは、赤ちゃんが言葉や文化、動作などを誰かに教えられなくても自然に習得していく様子を見れば、実感として納得できるかもしれません。
大人の言葉づかいや表情、家庭内の雰囲気など、良くも悪くも環境の全てを吸収してしまうということです。
赤ちゃんの脳は「吸収するため」にできている
実際、生まれたばかりの赤ちゃんの脳には、すでに約140億個の神経細胞(ニューロン)が存在しています。
この細胞同士が、視覚・聴覚・触覚などの体験によってつながり(シナプス結合)、神経回路が発達していきます。
この過程は「脳の可塑性」と呼ばれ、3歳ごろをピークに徐々に減少していくことが分かっています。
つまり、吸収力が最も高い時期に、どれだけ質の高い体験や環境を与えられるかが、その後の学び・人格・情緒の安定性に大きく影響するということです。
0~3歳(幼年期前期)は「無意識の吸収期」
0〜3歳の赤ちゃんは、モンテッソーリの言葉を借りると「無意識的記憶の時期」にあたります。
この時期は、自分で意識して学んでいるという自覚がないまま、周囲のものごとをまるでカメラのシャッターを切るように取り込んでいくのです。
大人が想像する以上に、赤ちゃんの五感はフル稼働しており、視線の動きや音への反応、手足の動きなどを通じて、世界を学んでいます。
だからこそ、0歳からの声かけ、環境整備、繰り返し体験が、その後の非認知能力や集中力の形成に深く関わってくるのです。
3~6歳(幼年期後期)は「秩序と意味をもって整理する時期」
3歳以降になると、赤ちゃんはただ吸収するだけでなく、整理し、再現し、意味づけする段階に入ります。
ここでは、すでに無意識に取り込んできたものをベースに、「なぜ?」「どうして?」といった思考力が育まれていきます。
たとえば、身の回りの物の名前や数、会話の文法、生活のルールなどを少しずつ意識的に使いこなし始めるのがこの時期です。
このとき、前期にどんなことを吸収したかで、後期の「整理」の質が大きく左右されるのです。
だからこそ、0歳からの関わりが未来をつくる
モンテッソーリ教育は「今できることを先取りしよう」ではなく、「今だからこそできる発達の芽を大切にしよう」という考え方に基づいています。
0歳はまだ早いのでは?と思われがちですが、この時期だからこそ吸収しやすく、学びやすい「黄金期」なのです。
- 絵本の読み聞かせ
- 語りかけ
- 整った生活リズム
- 自由に探索できる安全な環境
など、どれも「小さなこと」のように見えて、赤ちゃんの脳と心を豊かに育てる大切な投資になります。

感じたことを何でも吸収しちゃうなんて、赤ちゃんはすごいたこね~
0歳からできる!モンテッソーリ的関わり方5選

ここからは、いよいよ具体的な実践内容を紹介していきます。
①自分で「選ばせる」環境を整える
赤ちゃんのうちからでも、おもちゃで遊ぶようになったら「自分で選ぶ」経験は可能です。
選ぶことを促す環境づくり
- 子供用の安全な棚を用意し、一番下の段におもちゃを複数並べる
- 自分の手で届き、選べるようにする
- 材質や手触りの異なるものを用意すると◎
うちの娘はまだ生後2か月なのでさすがにこれは難しいですが、先んじて棚とおもちゃを用意しました。
おもちゃは今後も増えていく予定ですが、今のところプラスチック製の色んな仕掛けが備わったおもちゃや、音が鳴る布素材の人形などがあります。

②声かけは「ゆっくり・高めの声」で
0〜3歳は「言語の敏感期」と呼ばれています。
赤ちゃんは聞こえた音をすべて記憶しており、意味がわからなくても脳には蓄積され、脳の発達が促されています。
我が家での実践
- 顔を近づけ、口元を見せながら話す
- 普段よりゆっくり・高めのトーンで
- 「可愛いね」「今オムツ替えてるよ」などの、感じたことや実況中継をたくさん聞かせる
我が家では、「(名前を呼んで)可愛いね」と語りかけ、ほっぺをつんつんすると、娘がにっこり笑ってくれます。
これは単に親が癒されるためにやっていることですが、きっと脳の発達や情緒形成には役立っているはずです。
赤ちゃんへの語りかけのメリットや実践方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています!
③新しいことは「見せてから、やらせる」
モンテッソーリ教育では、大人が「やって見せる→子どもが真似る」が基本です。
実践方法
- まずはゆっくりと動作を見せる
- すぐに手を貸さず挑戦を待ち、試行錯誤を見守る
- うまくいかないときは手を添えて少しだけ背中を後押し
遊びもそうですが、話し方、食べ方、礼儀やマナーなど、子供はあらゆる面で大人を見て、善悪の区別なく吸収します。
うちの娘はまだ生後2か月なので少し先の話ではありますが、子供に何かを教えるときは「○○しなさい」ではなく、親が背中を見せてあげることが大事だと思います。

少し話は逸れたけど、何でも「親がお手本を見せる」が大事たこね~
④ゾーンに入ったら集中を邪魔せず「見守り」
赤ちゃんがひとつのことに夢中になっているとき、それは「フロー状態」と呼ばれ、集中のピークです。
フロー状態では、通常ではできないような高いパフォーマンスを発揮でき、難しい課題もいとも簡単に達成できると言われています。
モンテッソーリ教育ではこの状態を重要な時間と捉え、子ども達に極限の集中を体験させることのできる環境を整える、つまり大人が邪魔をしないことが重要だと考えられています。
具体的な実践法
- 集中しているときは話しかけたり、動かしたりしない
- 何かを教えたり手伝ったりしたくなったときも「見守り」を徹底する
- フロー状態が切れたあたりで「頑張ったね」と認める
少し余談ですが、僕は学習塾で生徒たちに勉強を教えています。
体感として、大人が一方的に説明するよりも、一生懸命考えて手を動かしてもらった方が覚えがよく、生徒たちも楽しく前向きに取り組んでくれます。
うちの娘はまだ生後2か月なのでまだおもちゃで遊ぶには早いのですが、モンテッソーリの考え方は実体験とも合致するので、我が家でも取り入れる予定です!

すぐに手を貸したくなっちゃうけど、ここはぐっと我慢たこ~
⑤「秩序」を大切にする
0〜3歳は「秩序の敏感期」と呼ばれています。
いつもと違う場所・時間・順番に強く反応し、恐怖や不安を覚えてしまいます。
「色んな経験」という意味では、知らないものにたくさん触れた方が良さそうに思えますが、モンテッソーリ教育では、この時期はそうすべきないと考えられています。
我が家での実践
- おむつ替えの声かけ、授乳の場所、寝るときのメリーの曲などをいつも同じに
- 知らない人に会わせすぎたり、知らない場所に連れていきすぎたりしない
- 子供の周りの物は「元の場所に戻す」を徹底する

特に生まれたばかりの病院で、たくさんの人が面会に来すぎるのは良くないと考えられているたこ~
おわりに

モンテッソーリ教育は、特別な人のための教育ではなく、すべての子供への教育に使える考え方です。
特に0歳から3歳の時期は、「自己教育力」が爆発的に育つタイミング。
難しいことをしなくても、環境・声かけ・見守りを少し意識するだけで、赤ちゃんの可能性はどんどん広がります。
僕はまだ学んだだけで実践できていないことも多いので、
今後も、我が家で実践しながら、また記事を書いて紹介していきたいと思います。
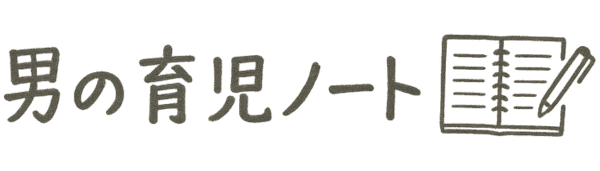
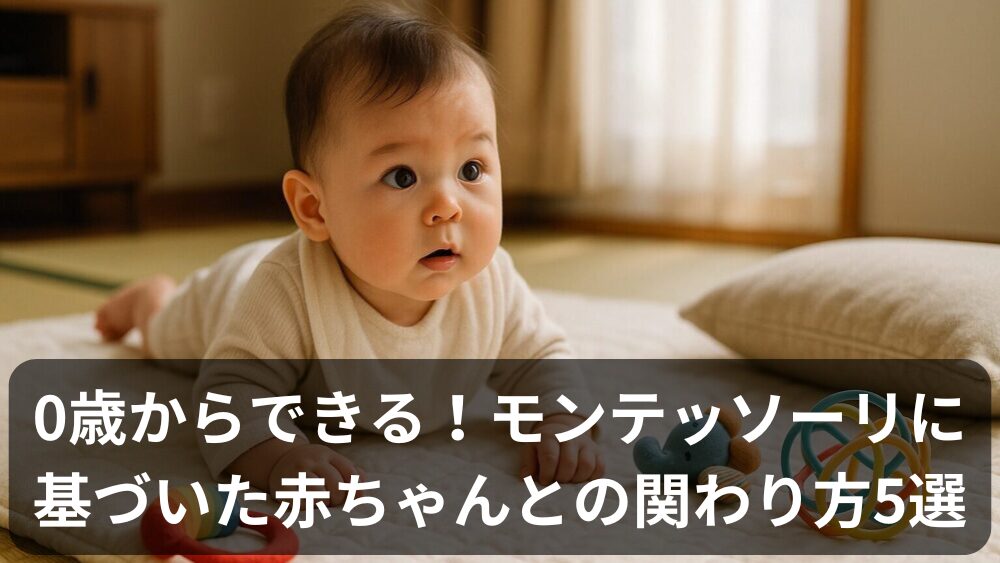



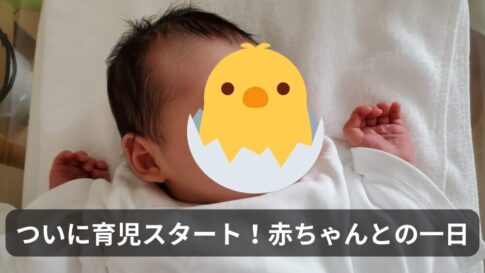




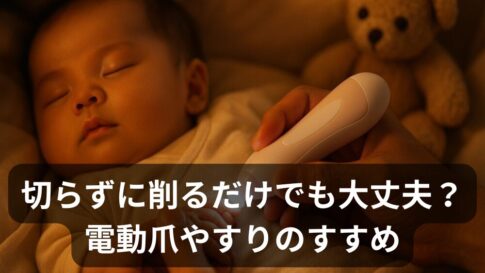
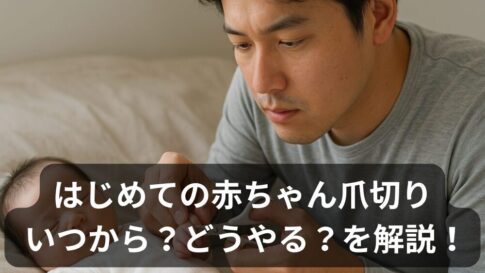

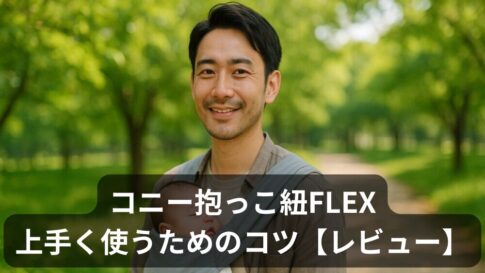
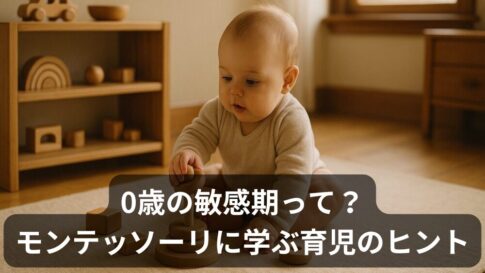




モンテッソーリ教育は「特別な施設」じゃなくて、「家庭」でもできるんたこよ~