はじめに
育児アイテムの中でも意見が分かれるのが「おしゃぶり」ですよね。
「泣き止ませるためには便利」と聞く一方で、「クセになるから使わない方がいい」という声もあり、迷う方も多いのではないでしょうか。
我が家でも、おしゃぶりの使用についてかなり悩みましたが、最終的には「外出時だけ限定的に使用」というスタイルに落ち着きました。
この記事では、おしゃぶりのメリット・デメリット・種類の違いに加え、実際に我が家でどのように使っていたかを紹介します。
おしゃぶりのメリット

おしゃぶりには、赤ちゃんにも親にもプラスになる面がいくつかあります。
①泣き止ませに効果がある
赤ちゃんは「吸う」という行為に安心感を覚えます。
おしゃぶりは母乳やミルクを飲む動作に似ているため、不安やぐずりの軽減に役立ちます。
特に、授乳以外での気分転換や落ち着かせたい場面で便利です。
②入眠の補助になる
眠たいのにうまく寝られない赤ちゃんにとって、おしゃぶりの吸啜行動が睡眠導入の助けになることがあります。
スムーズな寝かしつけのサポートとして、夜間の育児が少し楽になるかもしれません。
③SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスク軽減が期待されている
いくつかの研究では、おしゃぶりの使用がSIDSの予防に効果がある可能性が示されています。
【SIDS(乳幼児突然死症候群)とは】
健康だった赤ちゃんが突然亡くなる原因不明の現象です。
日本では年間100件前後の報告があり、生後2〜6か月に多い傾向があります。
おしゃぶりがSIDS予防に良いとされる理由には以下のような仮説があります。
- おしゃぶりで舌の位置や気道の確保がされやすくなる
- 眠りが浅くなり、異変に気づきやすくなる
- うつぶせ寝や深い睡眠への移行を抑える
ただし、確実な予防策とは言えず、授乳とのバランスや衛生面に配慮した使い方が前提です。
おしゃぶりのデメリット
便利な反面、デメリットや注意点もあります。
授乳への悪影響の可能性
母乳育児をしている場合、赤ちゃんが乳頭混乱を起こすこともあります。
吸い方が混乱して授乳がうまくいかないケースがあるため、新生児期に頻繁に使うのは注意が必要です。
クセになりやすい
常に口にくわえていると、「おしゃぶりがないと寝られない」「泣き止まない」という状態になりやすいです。
卒業のタイミングも難しくなります。
歯並びへの影響
長期間使い続けると、歯の生え方やかみ合わせに影響が出る可能性があります。
特に2歳を過ぎても使用している場合は注意が必要です。
衛生面の管理が必要
外出先で落としてしまうと、雑菌がつく可能性があります。
こまめな洗浄や予備の持参が欠かせません。
おしゃぶりの種類と選び方
おしゃぶりには、形状や素材の異なるさまざまな種類があります。
くわえる部分の形状

- 丸型(さくらんぼ型):一般的な形状で、新生児でもくわえやすい
- オーソドンティック型(平べったいタイプ):歯列への影響が少ないとされ、近年人気が高い
- 中空タイプ:空洞があり柔らかい。吸う力が弱い子に向いている
メーカーによって呼称が異なる場合がありますので、注意してください。
素材・サイズ

- シリコン製:透明で丈夫。お手入れが簡単で長持ち
- 天然ゴム製:柔らかくて口当たりがよいが、アレルギーには注意
- サイズ:月齢別に設計されているため、「0〜3か月」「3〜6か月」など表記をチェックしましょう。

赤ちゃんによって合う・合わないがあるため、1〜2種類試してみるのがいいたこ~
我が家の使い方:外出時だけ限定使用

我が家では、おしゃぶりは「基本使わない派」でした。
ただし、外出先でどうしても泣き止まないときには頼ることもありました。
例えばこんなときです
- 電車やバスの中で周囲への配慮が必要なとき
- スーパーや病院の待ち時間で泣き続けてしまうとき
このような場面では、赤ちゃんの安心材料として非常に助かりました。
ちなみに使用していたのは、くわえる部分が平べったくなったオーソドンティック型です。
歯並びを気にした結果これになりましたが、あまり好きではないようで、くわえさせてもすぐに吐き出してしまうこともあります。
ですがあまりおしゃぶりにハマりすぎても良くないので、一旦これで乗り切っています。
知り合いのお子さんもオーソドンティック型を使用していますが、あまり好んでくれていないみたいなので、平べったい形は子どもに人気がないのかもしれないと考えています。

それでも我が家では、歯並びが悪くなるのを一番心配しているたこね~
おわりに
おしゃぶりは、正しく使えば育児の助けになる便利アイテムです。
ただし、メリットとデメリットを理解し、使う場面や頻度をコントロールすることが大切です。
初めての育児では「使っていいの?」「やめたほうがいいの?」と迷うことも多いですが、赤ちゃんとご家庭に合ったスタイルを見つけていけたらいいですね。

おしゃぶりは賛否あるけど、うまく付き合えば助けになるたこ~!
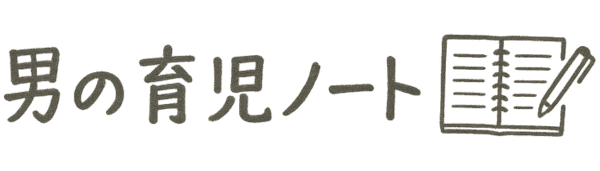
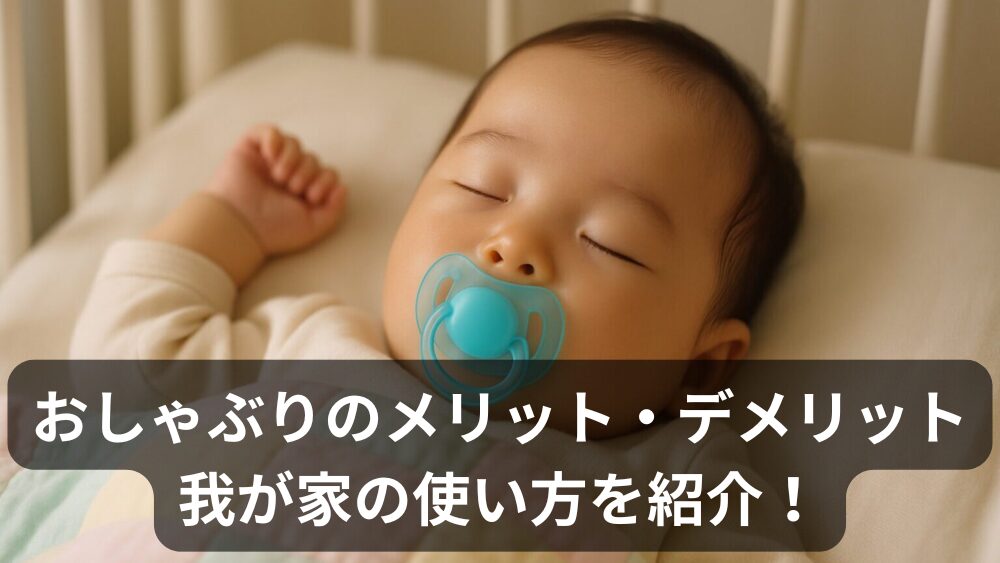
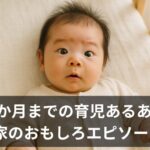

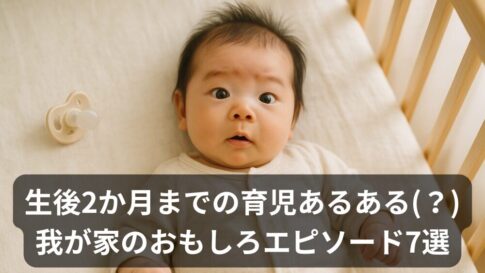


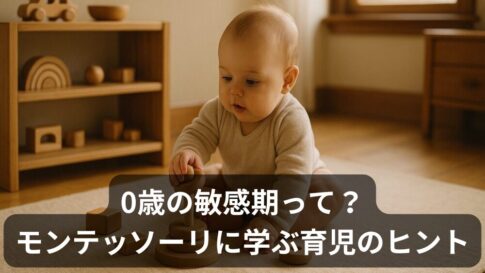


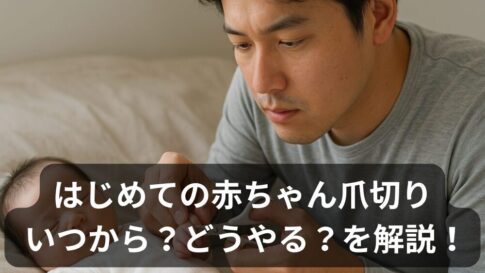


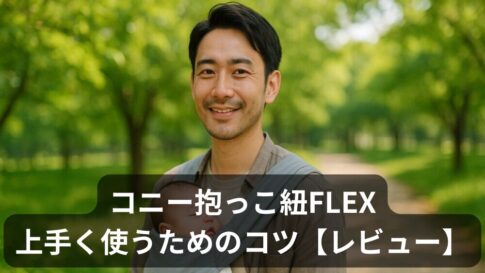




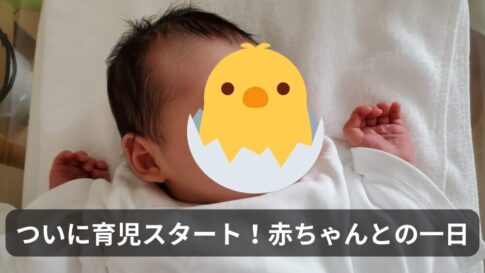

我が家は歯並びが悪くなることが気になったから、オーソドンティック型を選んだこ~