はじめに
赤ちゃんの成長は本当にあっという間です。
特に0歳の時期は、毎日のように新しい動きや反応が見られ、目まぐるしく変化していきますよね。
この行動って何か意味があるの?
というように、赤ちゃんの行動に戸惑ったり、どう関わればいいか悩む方にこそ知ってほしいのが、モンテッソーリ教育でいう「敏感期」です。
これは、ある特定のことに対して急激に興味や集中を示す時期のことで、脳や身体の発達と密接に関係しています。
この記事では、モンテッソーリ教育の視点から、0歳の敏感期の特徴を月齢別に紹介し、親ができる関わり方を提案します。
プレパパ・新米パパの方にもわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
モンテッソーリ教育についてはこちらの記事で詳しく紹介しています!
モンテッソーリ教育における「敏感期」とは?
モンテッソーリ教育でいう「敏感期」とは、子どもがある特定の能力を自然に身につけやすくなる一時的な期間を指します。
この期間に子どもは、自らの成長に必要なものを本能的に選び取り、驚くほど容易に習得していきます。
0〜3歳は「吸収する精神」とも呼ばれ、この時期に脳の神経回路の約80%が形成されるとされており、人生の土台となる大切な時期です。
子どもは五感を通じて周囲の刺激を無意識に吸収しており、適切な環境と関わり方が極めて重要になります。
敏感期の種類と0歳児の特徴
0歳児(生後0〜12か月)には、以下のような複数の敏感期が次々と現れます。
- 言語の敏感期
- 運動の敏感期
- 感覚の敏感期
- 秩序の敏感期
また、発達心理学の視点では、この時期は「愛着形成(基本的信頼感の獲得)」が最重要課題とされ、親の適切な応答が信頼関係を育む鍵となります。
ここからは、「0〜3か月」「4〜6か月」「7〜9か月」「10〜12か月」の4段階に分けて、月齢ごとの主な敏感期と発達の特徴、親の関わり方を紹介します。

赤ちゃんは色んなことに敏感になって、どんどん吸収していくんたこね~
0〜3か月:安心感と感覚の芽生えを育む時期

特徴
- 視覚・聴覚などの五感が急速に発達
- コントラストの強いものや人の顔に注目
- 泣き声や微笑みでコミュニケーションを開始
- うつ伏せで頭を上げられるようになる(首の筋力発達)
親の関わり方
- すぐに応答することで信頼感を形成
- 名前を呼んで語りかける
- 顔を近づけ、ゆっくり高めの声で話しかける
- 決まった場所・ルーティンを守ることで秩序感を育てる
- 我が家ではおむつ替えはベッド、授乳はソファ、寝るときはメリーをONにするなど、秩序を演出しています
- 集中しているときは邪魔せず見守る

生後2か月のうちの娘は、親が顔を近づけて笑顔で名前を呼ぶとにっこりしてくれて可愛いたこ~
我が家で購入したものも含め、メリーについてはこちらの記事で詳しく紹介しています!
4〜6か月:感覚の探求と運動の発達が進む時期

特徴
- 寝返りやおすわりが可能に
- おもちゃを握る・舐めるなど探索行動が活発に
- 喃語(ばぶばぶ等)が始まる
親の関わり方
- 安全対策を万全にした環境を整える
- うつ伏せ遊びなどで自発的な運動を促す
- 喃語に会話のように応じる
- 五感を刺激する布絵本や音の出る絵本を活用

うちの娘はまだ2か月だから寝返りもおすわりも無いけど、するようになったら可愛いんだろうな~
7〜9か月:自発的な移動と探索が始まる時期

特徴
- ハイハイ・つかまり立ち・人見知り・後追い
- 「いないいないばあ」や物の出し入れ遊びが増える
- 言葉の抑揚やリズムを真似る
親の関わり方
- 触ってもよい物だけを手の届く場所に置く
- 興味のあるものはできるだけ「ダメ」と言わず触らせる
- 探究心を満たす遊び(コップ重ね、型はめなど)を提供
- 親がお手本を見せてから挑戦させる(模倣させる)

真似をして学ぶなんて、とってもかしこいたこね~
10〜12か月:自立への第一歩と模倣が始まる時期

特徴
- 初めの一歩が見られる子も
- 「自分で!」の主張が強まる
- 食事や着替えに自主的に関わりたがる
- 模倣欲が強まり、掃除や電話のマネをする
親の関わり方
- 食事や着替えを一緒に取り組む
- 失敗しても手を出しすぎず「できた!」を増やす
- 親は「良い手本」として振る舞う
- 自分で選べる環境・道具(低い棚、小さな椅子など)を用意

僕も娘が自分からやりたがるようになったら、何でもやらせて出来るだけ見守るようにしたいたこ~
ちなみに、もう娘ようの棚を用意しちゃったこ~
おわりに:敏感期を知ることで、育児のストレスが減る

モンテッソーリ教育では、「子どもは生まれながらにして自分を育てる力を持っている」という考えがあり、これを自己教育力と呼んでいます。
そしてそれを信じ、その時期特有の発達欲求(=敏感期)を満たす環境を整えることが重要とされています。
「なぜこんなことをするのか分からない…」と悩むより、「今はどんな敏感期なのか?」を知れば、子どもの行動に意味があることがわかり、イライラも減るはずです。
モンテッソーリのこの言葉を胸に、教えるのではなく、見守り、必要な環境を整えるという関わり方を、あなたの家庭でもぜひ取り入れてみてください!
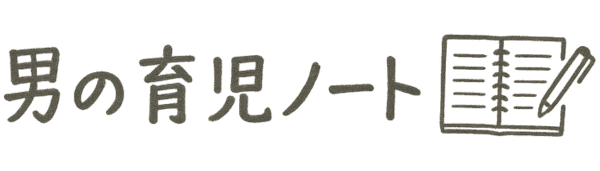
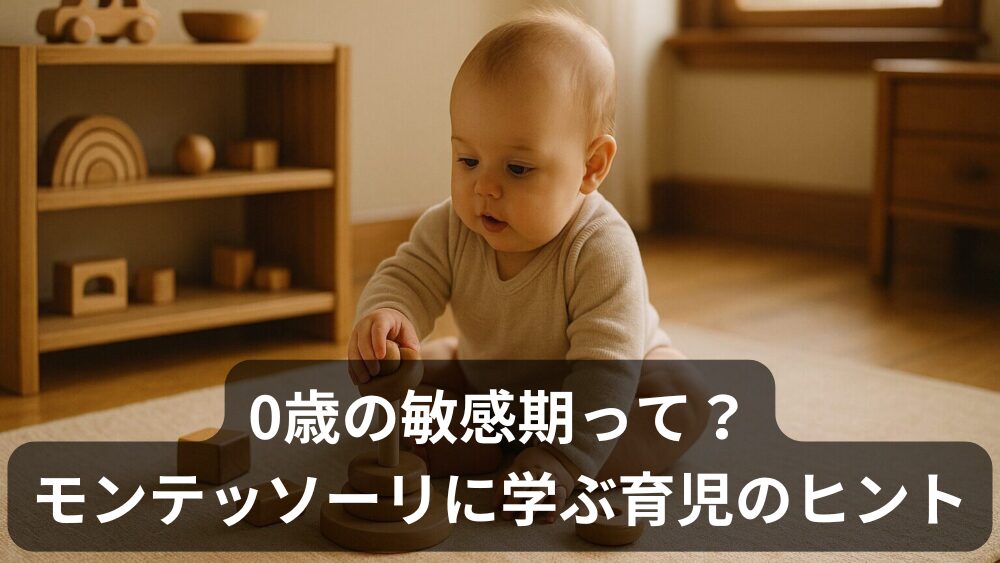



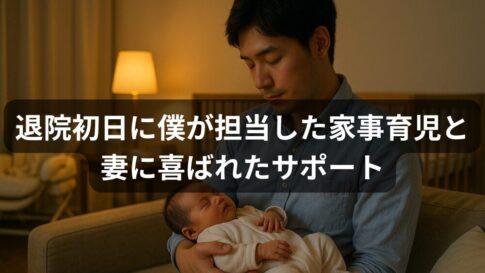
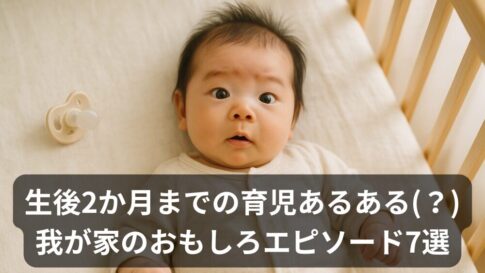




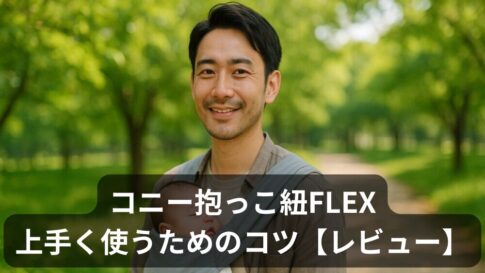


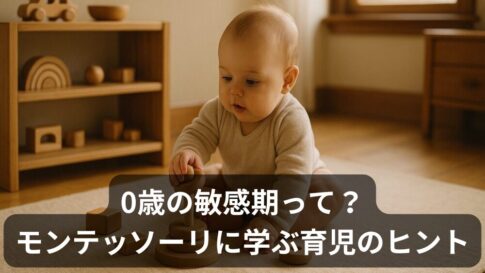




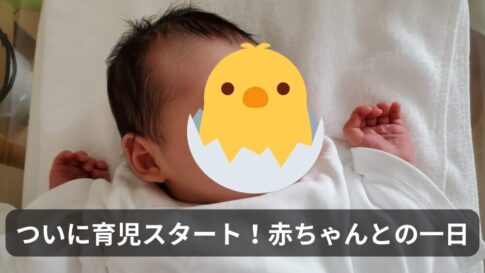
敏感期を知っておくと、赤ちゃんの行動の「なんで?」のヒントになるたこ~