はじめに
赤ちゃんが生まれて3週間ほど経つと、それまでとは明らかに様子が変わってきた…そんな経験はありませんか?
それは、俗に言う「魔の3週目」です。
我が家でも、生後3週を過ぎた頃から赤ちゃんの様子が急に変わり、戸惑う場面が増えました。
この記事では、
- 「魔の3週目」とは何か
- 主な症状や原因
- パパ・ママができる対処法
をパパ目線の実体験を交えて解説します。
「魔の3週目」って何?
「魔の3週目」とは、生後3週目前後の赤ちゃんに見られる情緒や身体の急な変化のことです。
医学的な正式名称ではありませんが、多くの新生児に共通して見られる現象として知られています。
この時期は、赤ちゃんが急速に成長・発達する過程で、心身のバランスが一時的に崩れると考えられています。
よくある症状と変化

泣く時間が急激に増える
これまでスヤスヤ眠っていた赤ちゃんが、突然理由もなくギャン泣きするように。
我が家でも、生後15日目を過ぎたあたりから泣く時間が明らかに長くなり、一日中泣いていることもありました。
具体的にはこんな感じになります。
- 泣いている原因が分からず、親も混乱する
- それまでは抱っこすると泣き止んでいたのに、泣き止まない
- 夕方~夜にかけて特に泣きやすい(いわゆる黄昏泣き)
【黄昏泣きとは】
黄昏泣きとは、夕方から夜にかけて赤ちゃんが理由もなく激しく泣くことです。
生後2〜4週頃に始まり、3か月頃まで続くことがあります。
主な原因は「日中の刺激や疲れの蓄積」「睡眠リズムの未発達」「神経の発達による不安定さ」などと言われています。
明確な理由がなくても泣き続けるため、あまり思いつめず、静かな環境で寄り添うことが大切です。
授乳の間隔がバラバラになる
これまで比較的規則的だった授乳のリズムが、急に乱れてきたように感じることがあります。
例えば、3時間ごとに授乳していたのに、急に1〜2時間で泣くようになったり、逆に4〜5時間眠り続けて授乳が遅れることもあります。
この現象の主な原因は以下の3つです。
① 成長にともなうエネルギー消費の増加
この時期の赤ちゃんは、筋肉や神経の発達が活発になり、手足をバタバタ動かしたり、声を出したりすることが増えてきます。
それによって体力を多く使い、エネルギー消費が激しくなるため、お腹が空くペースが速くなることがあります。
② 消化器官の成長と個人差
腸や胃の機能が少しずつ発達していく時期ですが、まだ未熟なため、一度に飲める量や消化速度にばらつきがあります。
そのため、「ちょこちょこ飲み」になって頻繁に授乳を欲しがる子もいれば、飲みすぎて間隔が空く子もいるなど、赤ちゃんによって違いが出てきます。
③ 泣き方の多様化と“泣き=空腹”の誤解
この頃から赤ちゃんの泣き方が変わり始め、空腹だけでなく、眠気・不快感・黄昏泣きなどの理由で泣くことも増えます。
しかし親はその泣きを「お腹が空いたサイン」と受け取って授乳してしまうことも多く、本来の授乳リズムが乱れる一因になります。
「泣く=お腹が空いた」とは限りません。
眠い、暑い、かゆい、抱っこしてほしいなど、様々なサインを泣いて伝えようとします。
まずは焦らず、赤ちゃんの様子をよく観察してみましょう。
便の回数が減る・うなり声が増える
新生児期には1日に何度も出ていたうんちの回数が、突然1~2回に減ることがあります。
同時に、赤ちゃんが苦しそうに「うーうー」「んーっ」と唸る場面も増えてきます。
我が家でも、生後15日頃からこの傾向が見られました。
原因としては、以下のようなものが考えられます。
- 腸の動きが活発になってくる一方で、排便の力み方はまだ未熟なため、
- 腸の中にガスが溜まりやすく、違和感から唸ることがある
- 成長により腸の働きが整ってきたことで、うんちの回数が自然に減る
生理的な変化であり、便の性状(柔らかさや色)に異常がなければ心配はありません。

うちの子は苦しそうに唸ってばかりだったので、がんばって~と応援していたこ~
睡眠時間が不規則になる
これまではまとまって寝ていた赤ちゃんが、突然短時間で起きるようになったり、昼夜逆転のような状態になることがあります。
この背景には、以下のような変化があります。
- 脳や神経の発達により、浅い眠りと深い眠りの切り替えが始まる
- 睡眠リズムが未発達なため、一定のリズムをまだ保てない
- 日中の刺激や不快感によって、睡眠が分断されやすくなる
赤ちゃんの眠りはとても敏感で、少しの刺激でも起きてしまうことがあります。
この時期はまだ「生活リズムを整える」というよりも、赤ちゃんに合わせて親が柔軟に対応することが大切です。

うちの子は元々全然寝なくて泣いてばかりだったこけど、この時期は特に酷かったこ~
抱っこ要求が激しくなる
これまではベッドや布団に置いても眠れていたのに、置くとすぐ泣く・抱っこから離れると不機嫌になるという変化が見られるようになります。
これは以下のような理由からです。
- 感覚が発達し、親のぬくもりや声を強く求めるようになる
- 視覚・聴覚の発達によって、「一人にされた」と感じやすくなる
- 泣けば抱っこしてもらえるという因果関係を少しずつ理解し始める
特に夕方~夜にかけては、日中の刺激の蓄積と疲れで赤ちゃん自身も不安定になりやすく、抱っこを求める時間が長くなる傾向があります。

置くとすぐ泣く現象は「背中スイッチ」と呼ばれることがあるくらいみんな経験しているたこね~
「魔の3週目」の原因とは?

急速な成長・発達
この時期、赤ちゃんの脳や感覚器官は急激に発達します。
これまで気づかなかった光・音・肌の感触などの刺激を感じ取れるようになる一方で、まだそれを処理する能力が未熟なため、不快感につながりやすくなります。
神経系の過渡期
脳や神経が急成長するこの時期は、刺激への反応が非常に敏感になります。
一見「理由もなく泣いている」ように見えるのは、視覚・聴覚・触覚などの刺激にうまく対処できない不安感の現れかもしれません。
これは赤ちゃんの神経系が働き始めた証なので、落ち着いた環境で寄り添うことが大切です。
消化器官の未成熟
腸の動きがまだ不安定で、便秘やガス溜まりなどが起きやすい時期です。
その結果、赤ちゃんはお腹が張って苦しそうにうなったり、便の回数が減ったりといった変化が見られることがあります。
昼夜逆転・生活リズムの未確立
生後1か月頃までは、赤ちゃんに昼夜の感覚(概日リズム)がまだ備わっていません。
そのため、昼にぐっすり眠ったかと思えば、夜に目が冴えて泣き続けるなど、睡眠のリズムも乱れがちです。
情緒の発達と分離不安
少しずつ親の存在を認識し始め、ママやパパと離れると不安を感じるようになります。
抱っこを求めて泣いたり、寝かしつけに時間がかかるようになったりするのは、この時期に多く見られる現象です。
「魔の3週目」は赤ちゃんの神経や感情、体の機能が目まぐるしく発達している証拠でもあります。
日中の刺激が多かったり、母乳やミルクのリズムがズレたりすることで泣く時間が増えることもありますが、一時的な変化であり、成長にとって自然なプロセスです。

親は焦るし大変だけど、正常なことなら良かったこね~
我が家で試して効果のあった対処法
①ひたすら抱っこしてあげる

体力的には大変ですが、スキンシップと安心感は、赤ちゃんにとって最強の安定剤でした。
泣き止まないときは、横抱き・縦抱き・抱いたまま家の中を散歩など色々試しました。
泣き声に心が折れそうになる日もありましたが、抱っこすればするほど、子供の可愛さにメロメロになりました。
我が家はねんねトレーニング(ねんトレ)をガチで取り組む方針ではなかったので、出来るときはとことん抱っこしてあげていました。
ねんトレについてはこちらの記事でまとめています!
②腸のケアに注目する(便秘・ガス対策)

便秘気味・ガスが溜まっているような場合は、以下のようなケアが有効でした。
- ベビーマッサージ(お腹を「の」の字にさすってガス抜きをサポート)
- 綿棒浣腸(回数ややり方は必ず小児科に相談のうえ実施)
- ミルクの調整(消化に優しい種類に変更してみる)
母乳・ミルクの種類によって、赤ちゃんの便の状態や消化のしやすさは変わることがあります。
心配なときは、市の保健師さんや小児科で相談してみるのがおすすめです。
③夫婦で交代制を取り入れる

親の寝不足・疲労・不安が重なりやすい時期なので、夫婦で「完全ワンオペにならないような工夫」がとても大事だと感じました。
我が家では以下のような工夫をしていました。
- 基本は妻が育児を担当しているが、出来るときは僕がおむつ替え・抱っこ・散歩・ミルクあげを担当
- 自分が動けるときはずっと抱っこし、そのまま家事や在宅仕事などをする
仕事もあるとは思いますが、出来るときはパパが積極的に育児に関わるだけで、ママの心も体もかなり楽になると思います。

我が家の魔の3週目は子供が一日中泣いて大変だったから、助け合いの精神が大事だったこ~
おわりに
「魔の3週目」は、育児の中でも最初の試練かもしれません。
でも、これは赤ちゃんがしっかり成長している証拠でもあります。
僕自身、この時期にはたくさん悩み、疲れ、「これが育児か…」と打ちのめされた気分になりました。
でも、乗り越えた今となっては、妻や子供との大切な時間だったと感じています。
泣き止まない赤ちゃんを前に不安になったとき、この記事が少しでもヒントや励ましになれば嬉しいです。
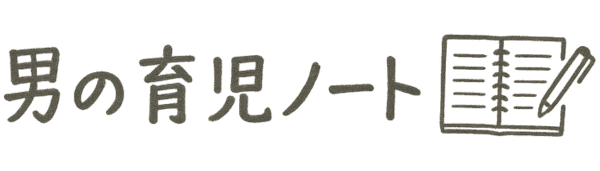
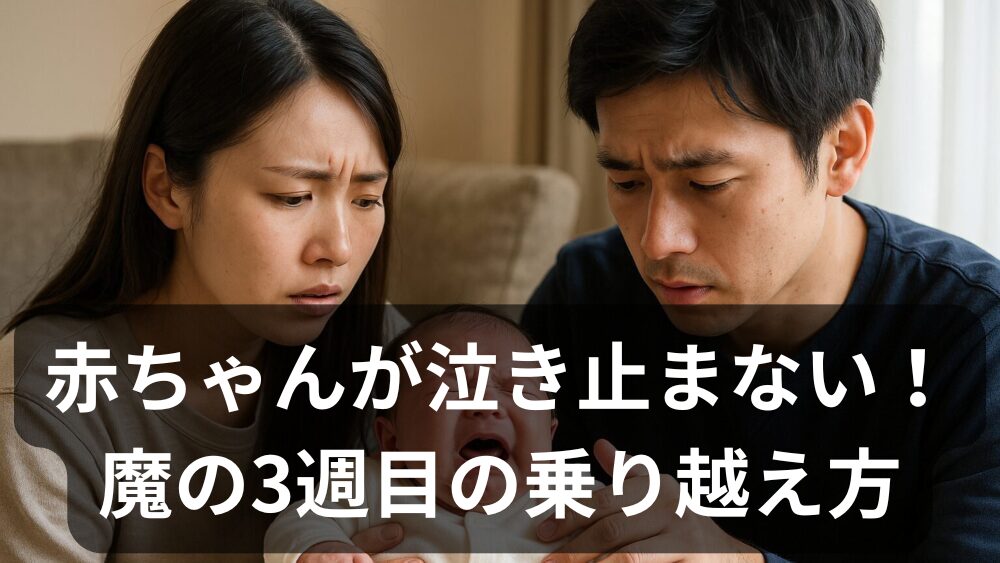



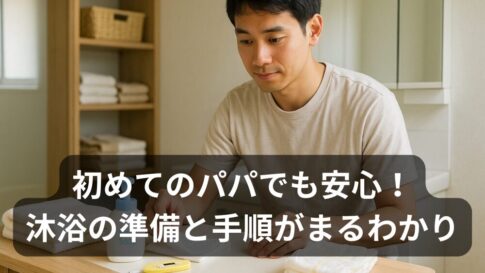
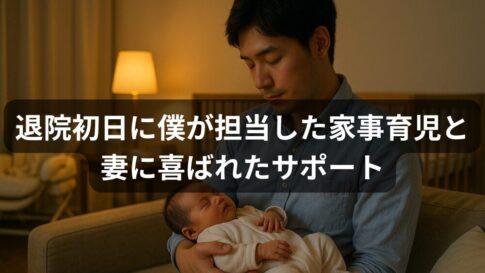



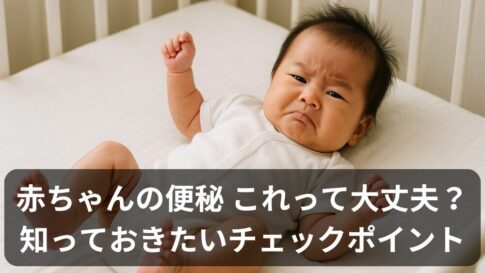


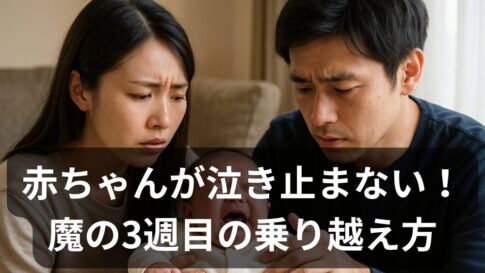


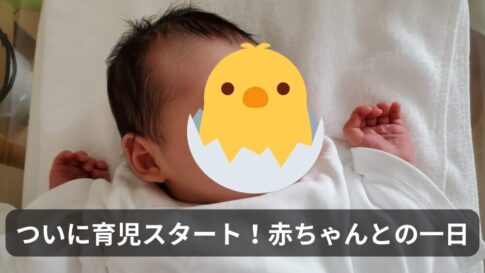



泣く理由の答え合わせは難しいたこね~